「それで響いてくる感じがする?」
「それで心が動くかな?」
「うーん、まだまだかも……」
一見、優しげな「悪魔の甘いささやき」に惑わされないように、「厳しい神の声」
を返すのが私の役割です。ここまで見つめてきた自分の強みを活かして、弱み
を乗り越えてゆくにはどうしたらよいか?無意識の衝動に歯止めをかける「言葉」
が見つかるのか?イメージマップを作り、模索しました。


「なぜそれが大事なの?」
「どうすればそうなるの?」
宣言する内容が固まってきたら、それが宣言するに値するものなのかどうか
判断するために、なぜその宣言が自分にとって価値を持つのかということと、
どうやって宣言したことを実現するかを示さなければなりません。
「一秒、一秒大切にっていう宣言にしようかな?」
「なぜそう思うの?」
「スクールに遅刻しないとか、寝坊しないとか……」
「確かにそれは大事だけど、いろいろな場面で自分にふりかかってくる選択を
賢く判断するためにその言葉は効き目がありそうかな?」
「……」
「人の顔色を見ないって宣言にする!」
「なるほど、それは君の弱点だからだよね。でも、宣言はやっぱり自分の強みを
活かして~しよう!っていうものの方が、どんなときでも踏ん張れて元気が出て
くるんじゃないかな?」
「……」
ひたすら「神の声」を返し、練り直す作業を続けているうちに、子どもたちもイライラ
してきます。ある子が厳しい目つきで私を見てたずねました。
「ねえ、大人はちゃんと決意とかしてるの?」
素晴らしい質問です。実は、多くの大人が真剣に決意宣言をせず、なんとなく
生きているのが実状です。
「全くその通り。大人だって君達みたいにやってないよ。よし、わかった。ぼくも
決意宣言をしよう!」
“私は子どもたちの学び続ける力を育てる人になります!なぜなら学び続ける力
がなければ、状況に応じて自ら知識を創り出して、解が簡単に見出せない問題に
対処することはできないからです。そのために私は探究する力を伸ばすテーマ
学習のあり方について追究します。”
探究教師は、共に探究する仲間として、子どもたちに「見本」を示すのですが、
それは単に「形」だけ見せればよいというような単純なものではありません。
このような瞬間を見逃さず、子どもと同じ課題に全力で取り組んでいる姿を見せる
ことが求められるのです。
しだいに、言葉ができあがってきますが、書いているだけでは、それが「伝わる」
ものなのかどうかはっきりしません。そこで、実際に声を出して読み上げてみます。
すると、なんとなくしっくりこないところがわかります。
「『役立つ』だとそれだけやる感じだけど、『役立てる』だと関係なさそうなことも
ちゃんと活かすっていう意味になるんだよね」
「夢を持ち『たい』じゃいし、夢をも『つ』でもないし、夢を持『て』だなあ」
「自分優先っていうのは、自分に甘いっていうこととは違うということをきちんと
説明しないと自分に優しいということの意味が伝わらない気がする」
素晴らしいつぶやきが子どもたちからこぼれでてきました。
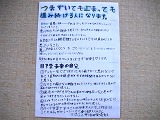
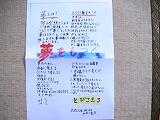
一語、一語。一文字、一文字。文のつながり……心に響く宣言にしようと真剣に
思えばこそ、そういった要素まで必然的に目が向いてしまうのです。作り直しに
つぐ作り直しにもかかわらず、もういいやと投げ出す子どもが一人もいません
でした。より完璧なものに近づけるため、黙々と作業していたのが印象的でした。
理性にも、感性にも訴えかけてくる力を持ち、無意識に動く前に、選択肢を意識し
ふみとどまって考えることを促す「魔法の言葉」をなんとか練り上げました。
RI
※TCS2009年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。
「それで心が動くかな?」
「うーん、まだまだかも……」
一見、優しげな「悪魔の甘いささやき」に惑わされないように、「厳しい神の声」
を返すのが私の役割です。ここまで見つめてきた自分の強みを活かして、弱み
を乗り越えてゆくにはどうしたらよいか?無意識の衝動に歯止めをかける「言葉」
が見つかるのか?イメージマップを作り、模索しました。


「なぜそれが大事なの?」
「どうすればそうなるの?」
宣言する内容が固まってきたら、それが宣言するに値するものなのかどうか
判断するために、なぜその宣言が自分にとって価値を持つのかということと、
どうやって宣言したことを実現するかを示さなければなりません。
「一秒、一秒大切にっていう宣言にしようかな?」
「なぜそう思うの?」
「スクールに遅刻しないとか、寝坊しないとか……」
「確かにそれは大事だけど、いろいろな場面で自分にふりかかってくる選択を
賢く判断するためにその言葉は効き目がありそうかな?」
「……」
「人の顔色を見ないって宣言にする!」
「なるほど、それは君の弱点だからだよね。でも、宣言はやっぱり自分の強みを
活かして~しよう!っていうものの方が、どんなときでも踏ん張れて元気が出て
くるんじゃないかな?」
「……」
ひたすら「神の声」を返し、練り直す作業を続けているうちに、子どもたちもイライラ
してきます。ある子が厳しい目つきで私を見てたずねました。
「ねえ、大人はちゃんと決意とかしてるの?」
素晴らしい質問です。実は、多くの大人が真剣に決意宣言をせず、なんとなく
生きているのが実状です。
「全くその通り。大人だって君達みたいにやってないよ。よし、わかった。ぼくも
決意宣言をしよう!」
“私は子どもたちの学び続ける力を育てる人になります!なぜなら学び続ける力
がなければ、状況に応じて自ら知識を創り出して、解が簡単に見出せない問題に
対処することはできないからです。そのために私は探究する力を伸ばすテーマ
学習のあり方について追究します。”
探究教師は、共に探究する仲間として、子どもたちに「見本」を示すのですが、
それは単に「形」だけ見せればよいというような単純なものではありません。
このような瞬間を見逃さず、子どもと同じ課題に全力で取り組んでいる姿を見せる
ことが求められるのです。
しだいに、言葉ができあがってきますが、書いているだけでは、それが「伝わる」
ものなのかどうかはっきりしません。そこで、実際に声を出して読み上げてみます。
すると、なんとなくしっくりこないところがわかります。
「『役立つ』だとそれだけやる感じだけど、『役立てる』だと関係なさそうなことも
ちゃんと活かすっていう意味になるんだよね」
「夢を持ち『たい』じゃいし、夢をも『つ』でもないし、夢を持『て』だなあ」
「自分優先っていうのは、自分に甘いっていうこととは違うということをきちんと
説明しないと自分に優しいということの意味が伝わらない気がする」
素晴らしいつぶやきが子どもたちからこぼれでてきました。
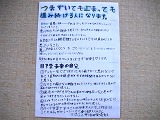
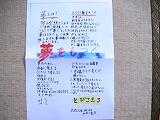
一語、一語。一文字、一文字。文のつながり……心に響く宣言にしようと真剣に
思えばこそ、そういった要素まで必然的に目が向いてしまうのです。作り直しに
つぐ作り直しにもかかわらず、もういいやと投げ出す子どもが一人もいません
でした。より完璧なものに近づけるため、黙々と作業していたのが印象的でした。
理性にも、感性にも訴えかけてくる力を持ち、無意識に動く前に、選択肢を意識し
ふみとどまって考えることを促す「魔法の言葉」をなんとか練り上げました。
RI
※TCS2009年度探究テーマ一覧は、こちらよりご覧ください。
