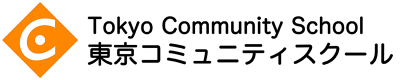【探究領域】自主自律
【セントラルアイディア】栄養は生きる勇気。
<テーマ学習> 〜レポート
このテーマ学習では「栄養は生きる勇気」というセントラルアイディアを実感するために、食べ物がどのようにして私たちの身体の栄養となっていくのかを知り、さらに心の栄養についても探究をしていきます。
まず1週目は「栄養」や「勇気」について、どんなイメージをもっているのかを子どもたちに尋ねてみると、食べ物、エネルギー、睡眠、運動、健康、元気などに関わる話題をあげてくれました。からだの栄養は、毎日の生活として食事があるのでイメージがつきやすい様子でした。
「それでは食べ物は体の中でどうなっていくんだろうね」ということで、自分が知っている(イメージする)食べ物の運ばれ方を図に描いてもらいました。子どもたちそれぞれに知っていることは違っていましたが、最終的に便(いらないもの)になることは明らかな様子でした。


体内の消化に関する動画を観たり、図鑑を広げたり、図鑑の図に沿って通り道を確認したりした上で、興味のある消化器官の模型を作ることになりました。
この工作が、子どもたちにとって、消化器官と向き合う機会になることを感じた場面となりました。作っていくうちに、どうなっているのかを観たり説明を読んだりして、自分の身体の中で無意識のうちに起きている生理現象を知ることになり、みんな自分ごととして関心を高めていきます。これは、事実の記載された説明文を読めば理屈ではわかりますが、「実際に手を動かして工作に取り組む」という過程が子どもたちにとって時間をかけてゆっくり向き合う時間になっているように感じられました。
「見た目や構造の特徴はなんだろう?」
「どんな素材なんだろう?」
「胃は何をするところなの?どんな機能があるの?」
「ぜんどう運動ってなんだ?」
「小腸の中には毛が生えているの???」

その工作品を活用し、互いにシェアする場面では、これをそのままプレゼンにしたいほどに、自分の腑に落ちたことを自分のことばで語り合い、情報が共有されていきました。
理科で唾液のデンプン反応を扱ったこともあって、唾液腺について熱く語ったり、十二指腸の名前の由来が述べられたり、食道・胃・腸でぜんどう運動が行われていることがわかったり、消化液・消化酵素によって食べ物から栄養素に変化して体に吸収されていることを知ることができました。
そこから、その栄養素がどんな食べ物に入っているか、どんなバランスで食事をすると良いのかを、クイズをしたり、実際の食事を見直したり、バランスの良い食事を考えたりしていきました。中には、小松菜のしらすあえがバランスよくなるメニューになるなどの発見があり、バランスよく食べる難しさを考えさせられる場面でもありました。
ぜんどう運動を確かめるために、寝そべったり、逆立ちしたりして、ビスケットを飲み込み、じーっと噛み砕いたビスケットが胃袋に送られていくのを感じる時間もありました。
「だいたい30秒くらい〜〜」と、それぞれ普段の食事では当たり前に起きている生理現象に寄り添っていました。
バランスの良い食事(栄養素の摂り方)と並行して、消化器官との繋がり、消化器官のそれぞれのFormやFunctionを確認したりしながら、「こころと栄養」ってなんだろうという疑問がクラスで湧き上がっていきました。
ある子が、「心(心臓または脳という意味で)は体の一部」と言いました。またある子は「心って脳にあるんだよ。だから胸の中じゃないんだよ。」と言いました。
「こころ」に話が進む前に、まずは、「こころとからだの繋がり」を意識してみることにしました。こころが楽しいと体が動いちゃう、逆に病気とかで体が辛いと心もプラスじゃないなどという話も出てきました。「こころ」は物質的には可視化されていないので、この3、4年生にとっては、つかみにくい概念なのだと改めて感じます。科学的根拠は明らかではないものの、昔から「腹がたつ」などの体内の消化器官にまつわる慣用句は多く存在していて、少し陰陽五行説(臓器と感情の繋がり)のようなものを紹介してみたり、消化器官にまつわる慣用句を調べてみたりもして、なんとか「こころとからだ」の繋がりのヒントを得ていった子どもたち。
子どもたちにとってより具体的にイメージしやすくするために、6つのスピリットを活用し、今年度一年で特に成長したことや来年度成長していきたいことを考えていきました。子どもたちに浸透しているTCSスピリットは、こころ(気持ちの部分)についても具体的なエピソードで語りやすくしてくれます。
そしていよいよプレゼンに向けて、「勇気宣言」として自分が弱くなっているとき、またうまくいかないときに自分の背中を自分で押してあげるような勇気が出る言葉を考え出して聴衆に向けて宣言します。
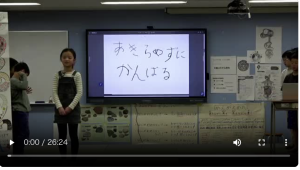
YI
(参考) TCSテーマ学習について、以下よりご覧ください。
・2024年度 年間プログラム(PDF)運用版
・テーマ学習一覧表(実施内容)